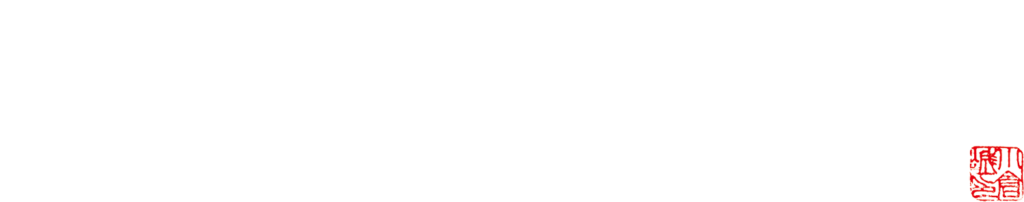第29話 小倉城の本丸を南北に挟む「北ノ丸」「松ノ丸」とは
前回の「小倉城ものがたり」では小倉城の中心であった本丸と本丸御殿を紹介しました。この本丸を南北に挟むように置かれていたのが、北ノ丸と松ノ丸、二ノ丸と呼ばれる区域です。
今回の「小倉城ものがたり」では、そのうち北ノ丸と松ノ丸を紹介します。それぞれ、どのような用途に使われていたのでしょうか。
小倉城の北ノ丸


北ノ丸は、本丸に対して「御奥ノ向(おおくのむき)」と呼ばれており、藩主の正妻の屋敷などがある私的性格の施設とされています。
細川氏の時代には、くちなしの木、うす色の椿、黄梅などが植えられていたそうです。細川小倉藩2代藩主・細川忠利は、北ノ丸で数寄(=茶の湯)を楽しむ一方、母・玉(細川ガラシャ)の月命日には終日精進していたといわれています。
小笠原氏の時代には、奥の御殿に加えて北ノ丸御殿が藩主と家族の住む場所となりました。小笠原小倉藩5代藩主の小笠原忠苗(ただみつ)は文化元年(1804年)に6代藩主・忠固(ただかた)に家督を譲って隠居した後、北ノ丸を居所にしました。
その後の北ノ丸跡
明治時代以降、北ノ丸跡は本丸跡と同様に何も置かれていませんでしたが、明治31年(1898年)に大日本帝国陸軍が本丸跡に第十二師団司令部を開設します。このとき、北ノ丸跡には第十二師団の経理部が置かれました。
しかし大正14年(1925年)に第十二師団が久留米市に移転すると、北ノ丸跡は再び空き地となります。
その後昭和9年(1934年)7月、それまで鋳物師町(いもじまち)にあった小倉城の守護神・八坂神社が遷座(せんざ=神仏を他の場所に移すこと)し、現在に至ります。
小倉城の松ノ丸

江戸時代に描かれた「豊前国小倉城図」(城下町の地図)には、松ノ丸の位置に「ゆうさい」とひらがなで記載されています。
これは小倉藩初代藩主である細川忠興の父・細川幽斎(ゆうさい)のことで、幽斎の屋敷が松ノ丸にあったと考えられています。
その後の松ノ丸跡
明治時代に入りしばらくの間、松ノ丸跡も本丸跡、北ノ丸跡同様に空いていたそうです。
明治18年(1885年)6月に、松ノ丸跡に歩兵第十二旅団本部が置かれます。現在松ノ丸跡にある白い門は、このときに使われていたもの(「歩兵第十二旅団本部正門」)です。
その後昭和11年(1936年)には、同じ小倉城内の二ノ丸跡より小倉市立記念図書館が移転してきました。しかし昭和21年(1946年)には米軍に立ち退きを命じられ、翌昭和22年(1947年)に西小倉小学校の一部に移転します。
そして昭和38年(1963年)、松ノ丸跡に白洲灯台の再現模型が建てられました。

白洲灯台とは、響灘の事故防止を目的として、幕末・明治時代の小倉藩の庄屋・岩松助左衛門が手がけた灯台のこと。小倉北区藍島の西方約2キロ、若松の沖合約5キロの岩礁(白洲)に立っています。
助左衛門が死去した翌年の明治6年(1873年)に完成し、現在立っているのは明治33年(1900年)築の2代目です。
毎年この再現模型近くで、助左衛門をしのぶための顕彰祭が行われています。
さいごに
前回・今回の2回にわたり、小倉城の本丸、北ノ丸、そして松ノ丸を紹介しました。
北は八坂神社のあたりから、南は松本清張記念館のあたりまでと、かなり広い区域で藩主とその家族たちが生活していたことがわかります。
周辺を一度歩いてみるとその広さがイメージできるのではないでしょうか。
参考文献:北九州市立自然史歴史博物館「小倉城と城下町」海鳥社、2020年
文:成重 敏夫