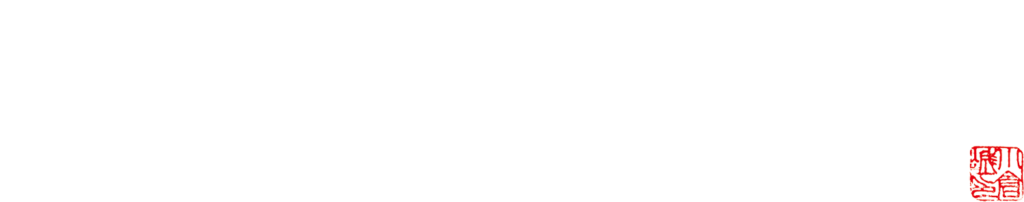第56話 紫川にかかっていた2つの橋常盤橋・豊後橋
小倉南区から小倉北区にかけて流れている紫川。
現在は下流を中心に多くの橋が架けられていますが、江戸時代にはわずか2本しか架けられていませんでした。
今回の「小倉城ものがたり」は当時の紫川に架けられていた2本の橋、常盤橋と豊後橋を紹介します。
常盤橋(ときわばし)
2本の橋のうち、河口付近に架けられていたのが「常盤橋」です。
初代小倉藩藩主・細川忠興は、小倉城の東を流れる紫川を天然の堀として利用し、海と堀に囲まれた小倉城を築きました。
このときに架けられた橋が常盤橋です。当時は大橋と呼ばれていたそうです。
この時代、小倉は九州咽喉の地(きゅうしゅういんこうのち)と呼ばれていました。
それは、常盤橋を起点に九州各地に繋がる五つの街道(門司往還、中津街道、秋月街道、長崎街道、唐津街道)が放射状に伸びていたことによるものです。
常盤橋は参勤交代の大名をはじめ多くの人に利用されており、享保14年(1729年)には第8代将軍・徳川吉宗に献上する白い象が渡ったという話が残されています。
また、文化7年(1810年)には日本各地を測量して地図を作った伊能忠敬が、文政9年(1826年)にはドイツ人の医師・シーボルトが常盤橋を訪れていることが記録されています。
平成7年(1995年)、常盤橋は江戸時代と同じ木の橋に生まれ変わりました。

豊後橋(ぶんごばし)
「豊後(ぶんご)」とは、現在の大分県(中津市・宇佐市を除く)のこと。
なぜ小倉の橋に「豊後」と名づけられているのか不思議に思う方も多いでしょう。
現在の豊後橋の主塔に、「豊国名所(とよくにめいしょ)」のレリーフが描かれています。「豊国名所」とは、小倉の町絵師・村田応成が、幕末期の小倉城下の様子や領内の名所、風俗を描いたものです。
この「豊国名所」の中に、豊後の農民によって紫川に木の橋が架けられる様子が描かれています。これが、「豊後」と名づけられている理由です。
現在の豊後橋は、昭和58年(1983年)に架け替えられたものです。楽器のハープを連想させる外観で、別名を「音の橋」といいます。
現在の紫川に架かっている橋
北九州市が昭和63年(1988年)に策定した都市計画「北九州市ルネッサンス構想」により、紫川下流の橋が整備されました。
国道3号線より下流には、現在10本の橋が架けられています。
海の橋(紫川大橋)
火の橋(室町大橋)
木の橋(常盤橋)
石の橋(勝山橋)
水鳥の橋(鴎外橋)
月の橋(宝来橋)
太陽の橋(中の橋)
鉄の橋(紫川橋)
風の橋(中島橋)
音の橋(豊後橋)
さいごに
現在の紫川には多くの橋が架けられており、東西の行き来も容易です。
しかし、江戸時代に架けられていたのはわずかに2本。外部からの敵の侵入を防ぐ意味合いがあるとはいえ、現代の感覚では少なく感じます。
しかし当時は、西曲輪に武士、東曲輪に町人と居住地が分かれていたため、行き来も頻繁でなかったことから、2本で十分だったのでしょう。
参考文献:北九州市立自然史歴史博物館「小倉城と城下町」海鳥社、2020年/北九州市ホームページ
文:成重 敏夫