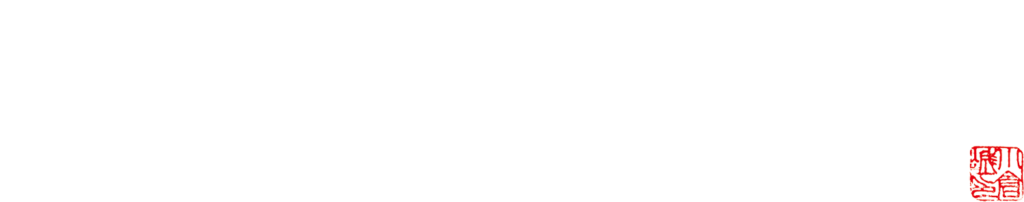第59話 庭園として長い歴史を刻む「小倉城庭園」
小倉城の入城施設として、平成10年(1998年)に開館したのが「小倉城庭園」です。
かつてこの場所には別の建物が建てられており、天守閣とは異なる歴史を紡いできました。
いったいどのような変遷を経て、現在の「小倉城庭園」となったのでしょうか。
現在の小倉城庭園

現在の小倉城庭園は、江戸時代の大名庭園と武家書院を再現し、茶室や展示棟を備えた複合施設です。
庭園ゾーンにある池泉回遊式庭園は、第5代藩主・小笠原忠苗(ただみつ)の時代につくられたものを再現したものです。
開館は平成10年(1998年)9月20日。この年には8月4日に北九州市立松本清張記念館もオープンし、小倉城天守閣周辺がほぼ現在の形となりました。
松井家屋敷
細川家が小倉藩を治めていた時代には、細川家の家老として小倉藩初代藩主・細川忠興らを支えた松井家の屋敷がこの場所にありました。
忠興の父・細川藤孝に仕えた武将に松井康之という人物がいます。
のちに忠興に仕えた康之は、中津藩の藩主となった忠興から豊後木付城(現大分県杵築市)2万5千石あまりを与えられ、九州の地に移り住むこととなりました。
その後、忠興とともに小倉藩に移った際、この場所に康之の屋敷が建てられました。
小笠原氏時代の御下屋敷
寛永9年(1632年)、細川氏のあとを継いで小笠原忠真が入国します。
小笠原氏が小倉藩を治めていた初期には、宮本武蔵の子・宮本伊織と忠真の父・秀政の家臣、小笠原主水が屋敷を2つに分けて住んだとされています。
のちに小倉に滞在した宮本武蔵は、伊織の住むこの屋敷に身を置いていた可能性が高いでしょう。
その後、小笠原忠苗の時代に和歌や茶道などを楽しむ下屋敷が完成。天守の下にあったことが理由で「御下屋敷(おしたやしき)」と呼ばれています。
天保8年(1837年)、小倉城は火災により天守閣、本丸御殿とともに焼失します。
このときは御下屋敷の焼失を逃れましたが、慶応2年(1866年)の第二次長州征討の際に焼失してしまいます。
明治以降
明治以降に小倉城内は軍用地となり、この一帯も整備されました。
明治31年(1898年)の「大日本帝国陸軍陸地測量部作製図」には、御下屋敷跡に池が描かれており、忠苗の時代に造成した御下屋敷の回遊式庭園にあった池が埋め戻されていないことが分かります。
そして、大正8年(1919年)の「小倉市街地図」では「遊園地」「紀念碑」と、昭和2年(1927年)の「東京工廠小倉移転に伴フ充当土地要図」では師団長官舎と記されています。
また、昭和8年(1933年)の「最新式小倉商工地図」では、陸軍の親睦施設が関わる保養所のような施設「勝山閣」が存在したと残されています。
さいごに
この一帯は、時代に合わせてさまざまな建物等が整備されていました。しかしどの時代も、庭園は一貫してはほぼ同じ位置に残されているものと考えられています。
「小倉城庭園」の歴史は比較的浅いですが、庭園そのものはずっと同じ場所で歴史を刻んできました。
参考文献:北九州市立自然史歴史博物館「小倉城と城下町」海鳥社、2020年
文:成重 敏夫