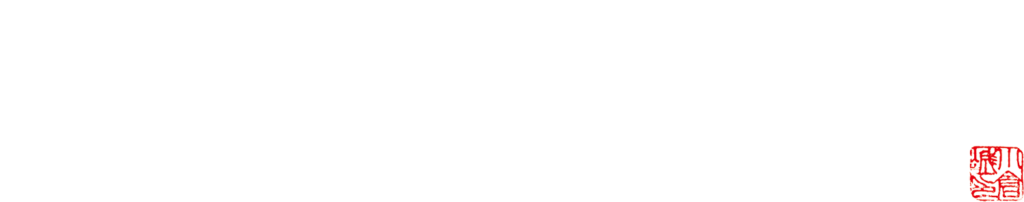第48話 小倉藩きっての“智勇兼備の名将”島村志津摩
小倉藩の礎は、歴代の藩主だけが作ったものではありません。藩主に仕える藩士もまた、小倉藩の繁栄を支えてきたのだと思います。
今回の「小倉城ものがたり」は、小倉藩の歴史に名を残す藩士・島村志津摩(しまむらしづま)を紹介します。
島村志津摩とは
島村志津摩は、天保4年(1833年)3月28日に小倉藩内で生まれました。天保13年(1842年)には、わずか10歳で家督となり、1200石の知行を相続します。
その後、嘉永5年(1852年)に弱冠20歳で家老に。政敵といわれた小宮民部より1年早い“出世”です。
「小倉戦争」での活躍
島村は、元治元年(1864年)の第一次長州征伐、および慶応2年(1866年)の第二次長州征伐で、一番備の士大将(さむらいだいしょう)として小倉藩軍の最高責任者を務めます。
ここで、小倉藩きっての“智勇兼備の名将”が存在感を発揮します。
第二次長州征伐内での戦のひとつ「小倉戦争」で、小倉藩は大苦戦します。慶応2年(1866年)6月17日に始まった「田野浦の戦い」で大惨敗、7月3日の「大里の戦い」でも敗戦し、後がなくなります。
ここで小倉藩は防衛体制を再編。赤坂地区に熊本藩軍を配属しました。その甲斐あって、次の「赤坂の戦い」で小倉藩は勝利を収めます。
島村は大里の戦い前夜から体調を崩していたそうですが、赤坂での激戦を聞き、救援に駆けつけたとの記録が残されています。
しかしここで総督の小笠原長行が戦線を離脱し、小倉藩は絶体絶命の窮地に追い込まれます。戦いの大義名分も失い、以降は長州藩との「私戦」へと発展します。
孤立した小倉藩は「力の限り防戦した上で小倉城を開城する」という方針を決定。
しかし、家老の小宮民部が独断でこの決定を覆します。
小倉城を自焼し、小倉藩は田川郡香春まで撤退することに。“政敵”小宮の判断は、島村にとっては寝耳に水のことだったといわれています。
香春に撤退した小倉藩は、島村中心に軍を再編します。
企救郡南部の金辺峠[きべとうげ](小倉南区呼野と田川郡香春町採銅所を結ぶ峠)及び狸山(現在の小倉南区朽網東)に防衛拠点を築き、高津尾(現在の小倉南インター近く)を前線基地として長州軍に遊撃戦を挑みます。
島村率いる小倉藩軍の奮闘は長州藩軍を慌てさせるも、勝利までには至らず。10月には長州藩軍が平尾台を占領します。
島村軍は金辺峠へ撤退しますが、それでも長州軍の攻撃は止まりません。
防戦一方となった小倉藩の内部では、止戦の話も出始めました。死力を尽くして戦ってきた島村も、これ以上の戦闘は難しいと考え止戦の提案を承諾。
小倉藩は長州藩との停戦交渉を開始します。交渉は難航しましたが、翌慶応3年(1867年)1月26日に和議が成立。小倉藩は藩の中心である小倉城下と企救郡を長州軍に明け渡し、事実上の降伏となりました。
藩校の再建
話は少し戻りますが、島村は小倉藩の重要課題として教育政策の具体化を掲げていました。
宝暦8年(1758年)に、第4代藩主の小笠原忠総が藩校「思永斎」を設立しました。のちに「思永館」と改称し小倉城に移転しますが、前述の小倉城自焼の際に思永館も焼失してしまいます。
島村は、敗戦の痛手から立ち直るためには人材の育成を通して藩の再興を図っていくしかないと考え、藩校の再建に取り掛かりました。
藩士の中で文武に長けていた喜多村侑蔵が島村の意を受け、慶応3年(1867年)に現香春町にある光願寺に「香春思永館」を開設します。
香春思永館は、終戦後の明治2年(1869年)に小倉藩が豊津藩へと改称されたことに伴い、「育徳館」と改称されました。現在の育徳館中学・高校のルーツにあたります。
また、「香春思永館」の名称も令和3年(2021年)に香春町内に開校した9年制の義務教育学校の校名に採用されました。
その後の島村志津摩
小倉戦争の講和後は香春藩の家老となりますが、明治2年(1869年)に辞職。明治9年(1876年)に44歳で逝去します。
当初は現在の京都郡苅田町に葬られていましたが、後年、広寿山福聚寺に改葬されました。
数多の戦功、そして教育の充実など、“智勇兼備の名将”が小倉藩に残したものは、決して少なくないでしょう。
参考文献:小野剛史 「小倉藩の逆襲」花乱社、2019年/白石 壽「小倉藩家老 島村志津摩」海鳥社、2001年
文:成重 敏夫