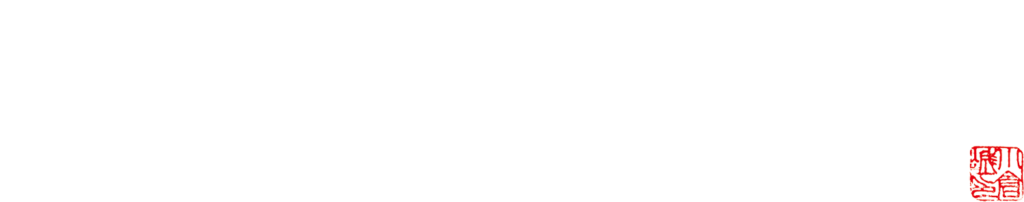第52話 私財を投じ白洲灯台の建設に尽力した岩松助左衛門
江戸時代の小倉沖は、潮流が速く激しいことから難破船が多く、「海の難所」と呼ばれていました。
そこで建てられたのが、白洲灯台(しらすとうだい)。
小倉北区藍島の西方約2キロ、若松の沖合約5キロの岩礁(白洲)に建てられています。
白洲灯台は、小倉城の松ノ丸跡に再現模型が建てられており、日本の灯台50選にも選ばれているので、ご存じの方も多いのではないでしょうか。
今回の「小倉城ものがたり」は、この白洲灯台の建設に長きにわたり尽力した、岩松助左衛門を紹介します。
岩松助左衛門とは
岩松助左衛門は文化元年(1804年)、企救郡長浜浦(現在の小倉北区長浜)で生まれます。
文政4年(1821年)に18歳で父の後を継いで長浜浦の庄屋になり、その後文久元年(1861年)まで約40年間庄屋を務めました。
助左衛門が頭を悩ませていたのが、小倉沖の難破船の問題です。当時、小倉沖を航行する船の数は万を超えるほどであったそうです。
関門海峡や玄界灘とつながっているので、潮流は速く激しく、時期によっては季節風の影響を強く受けて海域が大荒れに荒れることもあったそうです。遭難した例も少なくなかったといいます。
岩松助左衛門、難破船支配役に
小倉藩から、海難事故発生時及び事後の対応が高く評価され、助左衛門は庄屋を辞任した後に海の安全を守る「難破船支配役」を命じられました。
当時の助左衛門は難破船発生の連絡を受けると、救助加勢を伴うものであろうとなかろうと、必ず自ら藍島に急行しなければなりませんでした。
そこで助左衛門は、白洲に灯台を建て、ここが危険な場所であることを船に知らせることで事故が減るのではないかと考えます。
文久2年(1862年)、助左衛門が灯台建設の願書を小倉藩に提出。藩は建設を許可しますが建設のための資金は援助しませんでした。
そこで助左衛門は私財に加え、小倉沖を通る年間二万艘の船の関係者や地域の漁師などから寄付を集めて建設に充てました。
慶応3年(1867年)、小倉藩が「小倉戦争」で長州藩に敗れ、企救郡が長州藩の支配下に入ったことで、建設許可が反古となってしまいます。
しかし助左衛門はあきらめません。
長州藩からの仕事も誠実に実行して藩からの信頼を得た助左衛門は、明治元年(1868年)に長州藩に建設許可をお願いしました。
翌年長州藩は建設を許可を出すも、企救郡は明治3年(1870年)に日田郡の管轄下となり、またも許可が失効してしまいます。
その後、日田県から建設許可を得ることこそできたものの、このとき助左衛門は68歳。病に伏すことも目立つようになりました。
岩松助左衛門、灯台の完成を待たずに死去
明治4年(1871年)6月に政府から、私費による灯台の建設とそのための募金を禁ずる旨が助左衛門に通知されました。
これにより、白洲灯台の建設は国の事業として行われることになりました。
しかしこのとき、助左衛門の病状は悪化しており、8月には病床から離れることができなくなっていました。
明治5年(1872年)に、白洲灯台建設工事が開始。
しかし、灯台の完成を待つことなく、4月25日に助左衛門は死去します。
この年の11月に行われた仮点灯を経て、明治6年(1873年)9月に白洲灯台は正式の灯台となりました。
初代の白洲灯台は木造でしたが、明治33年(1900年)に石造りに改築。そして平成4年(1992年)に明治33年の姿に復元された3代目が完成しました。
助左衛門が私財を投じて建設した灯台は、近くを通る船が浅瀬に乗り上げることのないよう、今でも小倉沖を照らし続けています。
岩松助左衛門に関連する場所

毎年この再現模型近くで、助左衛門をしのぶための顕彰祭が行われています。
また、助左衛門の墓は小倉北区京町の西顕寺(さいけんじ)で、そして生家は同区長浜町で見ることができます。(現在は取り壊されております)
参考文献:江戸遺跡研究会「石原宗祐 僧清虚 岩松助左衛門(ふくおか人物誌)2」西日本新聞社、1994年、加藤 秀俊ほか「人づくり風土記 40:全国の伝承江戸時代 ふるさとの人と知恵 福岡」農山漁村文化協会、1988年
文:成重 敏夫