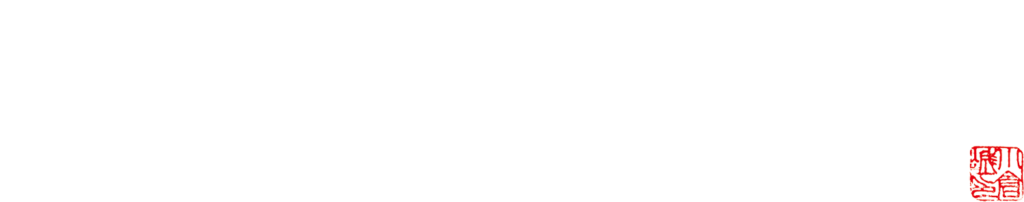第44話 お城の「天守」の四つの分類を解説
皆さんが、「お城」と聞いて一番にイメージするものは「天守閣(てんしゅかく)」ではないでしょうか。
天守閣とは、「城の本丸に築かれた三層または五層の構築物」のこと。
小倉城の天守閣は、お堀のそばにある五階建ての白い建築物です。

全国のお城には、江戸時代に作られたものや昭和に入り新たに作り直されたものなど、さまざまな天守閣が存在します。
今回はお城の天守閣がどのように分類されているかについて解説いたします。
天守とは
よく耳にする「天守閣」という言葉はいわゆる俗語で、正しくは「天守(てんしゅ)」と呼びます。
天守は政治権力の象徴ともいわれるほどの立派な建物なので、城主が住んでいる場所だと思われがちです。
しかし本来は軍事施設として使われるものなので、普段は空き家状態になっています。例外的に、安土城や大坂城がそれぞれ織田氏、徳川氏の住宅として使われていたという話が残されています。
よく、お城=天守と考えがちですが、天守はお城のごく一部にすぎません。
城主らが住む御殿や天守、蔵、櫓、門などの総称が「お城」です。
天守の種類
天守は大きく、「現存天守」、「復元天守」、「復興天守」、「模擬天守」の4種類に分類されます。
現存天守
現存天守とは、江戸時代までに建てられ、現在まで残っている天守のことをいいます。
ただし、必ずしも創建当時の建物がそのまま保存されているわけではなく、修復や改築、再建されたものも含まれています。
現在、日本国内の現存天守は12基しかありません。
全てに天守が存在したわけではないとはいえ、かつて城の数は2万を超えていたといわれる中、天守がわずか12基しか残っていないのはなぜなのでしょうか。
慶長5年(1600年)の関ヶ原の戦いで勝利した徳川家康は、全国の大名を統制するために、元和元年(1615年)に「一国一城令」及び「武家諸法度」を発令しました。
これにより、大名の居城である城以外は破却が命じられ、新たな城を築城することもできなくなりました。このとき、全国に3000以上あった城の大半が消滅したといわれています。
明治時代の廃城令により城郭の数はさらに減少。
1940年代には、現存する天守の数はわずか20基となりました。
その後、昭和20年(1945年)に第二次世界大戦のため7城の天守が、昭和24年(1949年)には失火により松前城の天守が焼失。
12城の天守を残すのみとなりました。
現存天守12城は以下の通り。
5つ(松本城、松江城、犬山城、彦根城、姫路城)が国宝に、7つが重要文化財に指定されています。
弘前城 【青森県】
松本城 【長野県】
丸岡城 【福井県】
犬山城 【愛知県】
彦根城 【滋賀県】
姫路城 【兵庫県】
松江城 【島根県】
備中松山城 【岡山県】
丸亀城 【香川県】
松山城 【愛媛県】
宇和島城【愛媛県】
高知城 【高知県】
復元天守
復元天守には、木造で忠実に復した「木造復元天守」と、鉄筋鉄骨コンクリートなどで、外観のみを以前の姿に復した「外観復元天守」があります。
「木造復元天守」には掛川城(静岡県掛川市)や大洲城(愛媛県大洲市)が、「外観復元天守」には名古屋城(愛知県名古屋市)や大垣城(岐阜県大垣市)、熊本城(熊本県熊本市)などが分類されます。
復興天守
復興天守とは、かつて天守が建てられていた場所に建てられたお城のことです。
史料不足などにより、当時の外観を正確に復元していません。
小倉城の天守はこの復興天守に含まれます。その他には大坂城や(大阪府大阪市)や小田原城(神奈川県小田原市)も復興天守に分類されます。
模擬天守
過去にその場所に城が存在していたものの、史実では存在しなかったのに建てられた天守、実物とは全く違う形状で建てられた天守を模擬天守と呼びます。
唐津城(佐賀県唐津市)、中津城(大分県中津市)などが模擬天守に含まれます。
次回の「小倉城ものがたり」
現在の小倉城の天守は、これら四種類のうち「復興天守」に分類されます。
次回の「小倉城ものがたり」では、築城当時の小倉城を国内の名だたる城の大きさと比べながら紹介いたします。
文:成重 敏夫