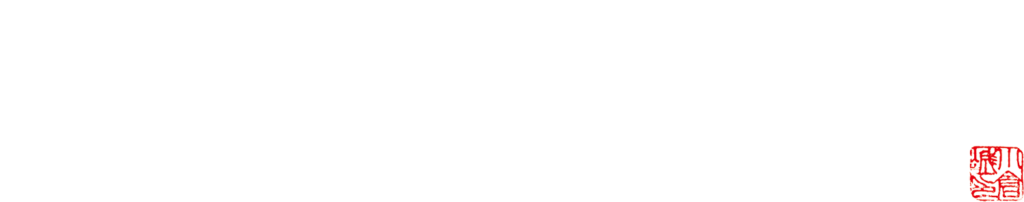第50話 万葉集が由来の「企救郡」はどの地域?
小倉には「企救(きく)」という名のつく地名や学校名、駅名があります。
企救丘〇丁目、企救丘小学校、企救中学校、北九州モノレール企救丘駅などがあり、しばしば「難読地名」として挙げられます。
この「企救」という地名は万葉集が由来とされています。
万葉集の中で、小倉から門司の大里にかけての海岸が「企救の長浜」「企救の高浜」と詠まれています。
かつては門司区、小倉北区、小倉南区の全域と八幡東区及び行橋市の一部を「企救郡」と呼んでいました。
今回の小倉城ものがたりは「企救郡」にまつわる話を紹介します。
企救郡は“山口県”に属していた?
慶応2年(1866年)に開戦した、長州藩(現在の山口県)との「小倉戦争」で不利な状況に置かれた小倉藩は、講和条件の一つとして小倉藩のうち企救郡のみを引き続き長州藩の占領下に置くことを要求されました。
敗色濃厚の小倉藩はこの要求を飲まざるを得ず、戦後も企救郡のみが長州藩の預かりのままとなりました。
その後、企救郡は明治2年(1869年)に日田県の管轄に移されます。
明治4年(1871年)には第1次府県統合により小倉県の管轄に、そして明治9年(1876年)には第2次府県統合により福岡県の管轄となります。
そして明治11年(1878年)に、それまでは単なる地理的区分であった「企救郡」が、行政区画(郡・区・町村など行政機関の権限の及ぶ範囲として定められた区画のこと)として新たに発足します。
当時は、門司区、小倉北区、小倉南区の全域と八幡東区及び行橋市の一部が「企救郡」とされていました。
明治22年(1889年)4月1日、町村制の施行により、企救郡内に以下の町村が発足します。
・文字ヶ関村
・小倉町
・柳ヶ浦村
・松ヶ江村
・東郷村
・足立村
・霧岳村
・曽根村
・朽網村
・芝津村
・城野村
・東紫村
・西紫村
・板櫃村
・西谷村
・中谷村
・東谷村
現在も残っている地名があるので、どの地域にあるのか分かる村もありますね。
その後、町制や市制の施行、合併などを繰り返し、昭和23年(1948年)9月10日 に東谷村が小倉市に編入したことで「企救郡」は消滅します。
「企救郡」は現在どうなっている?
上に記載されている町村のうち、城野村(現在の城野、横代、石田など)と東紫村(現在の北方、守恒、徳力、志井など)は明治40年(1907年)に合併し、「企救村」となりました。
現在の企救丘〇丁目、企救丘小学校、企救中学校、企救丘駅は、全てこの「企救村」のエリアに含まれています。
地名としては残っていなくても、地域の施設などに残されている村名もあります。
東谷(ひがしたに)村は地名としては残っていませんが、市民センターや中学校にその名を残しています。
中谷(なかたに)村も同様です。地名としては使われていませんが、小倉南インターチェンジ近くにある西鉄バスの営業所と停留所の名称には「中谷」が使われていますし、小倉と天神を結ぶ高速バスのうち、中谷停留所経由の系統には「なかたに号」の愛称がつけられています。
地名として残っているうちのひとつが、板櫃(いたびつ)村です。
現在の板櫃町は非常に狭いですが、明治22年(1889年)の町村制施行以降の板櫃村は現在の到津、原町、金田、中井、田町に加え、八幡東区の槻田、それに馬島、藍島まで含まれるほどの広さでした。
さいごに
現在、「企救」の名が入る地域はさほど広くありませんが、以前は門司と小倉と合わせたかなり広いエリアが「企救郡」に含まれていました。
万葉集を由来とする由緒ある地名であることと一緒に覚えておきたいですね。
文:成重 敏夫